
参考リンク:Wikipedia「ハトのおよめさん」
1999年よりアフタヌーン掲載中のショートギャグ、単行本はアフタヌーンKCとして刊行中。略称「ハトよめ」という今作は何かというと、メルヘンもどきなどうぶつの世界で、ごうまんとも変質的ともエゴイストとも形容しかねる珍キャラクター≪ハトよめ≫が家事の合い間に(?)、ボケたりツッコんだりビームを発射したり…と、大忙しィ~! といったまんが作品、なのでは?
われらのハトよめは格闘家でもスーパーヒロインでもないただの主婦、であるはずだが、どういうわけか、ビームを筆頭に多くの必殺技を身につけており。そしてわりと理不尽かつ気まぐれに、それらを繰り出して大暴れするのだった。
だいたいハトよめのいかしてるところとして、奥さまなのに口ぐせは『うるせえ』、『殺すぞ』、『いいから』。さいごのやつが、特にいい。筆者のごとき小物だと一生言えないような暴言らを、相手かまわず特に身分もないのに吐きまくっているハトよめ様、そこへの尊敬とあこがれが止まらない。
『うるせえ』といえば、「ハトよめ」単行本の第1巻の表紙がいきなり、『うるせえ』と言って彼女がいきなり夫にキックを入れている絵柄。すわっ、こいつはDV礼賛かッ!?
なお、『ダンナ』とか『あなた』とか呼ばれているハトよめの夫はベンチャー企業の社長なので、基本的にはおカネがある。そこらからこのファミリーらに関する描写には、バルザック「人間喜劇」チックな19世紀の≪仏自然主義≫、ブルジョワジーどもの醜行を赤裸々に描く、といったふんいきがなくもない。どこかちがうところでも、そんなことを申し上げたけど。
よって、われらがハトよめのあれこれとむやみな活躍らを、『有閑マダムの気まぐれ』とも見うる。と、そのように言ってみると、これがいっそうすてきな作品のような感じが…?
さてこのすばらしい創作について、いつかくわしく語れる機会があればいいのだが。いまとり急ぎ手短に、その世界でさんぜんと輝く≪狂気≫の兆候はというと…。
と言ってパラパラと今作を見ていたら、わりと最初の方に、こんな1コマが(第1巻, p.93, 『ハトビームの10』より)。
まずナレーション、『ハト一家はスキー場をめざしていました』。そして画面には野原の中の1本道を、オープンカーで走っているハト一家3羽の姿。
そうしてよめは、大きく翼を拡げてきもちよく、『わたしのスキーは誰にも 止められな~い♪ ついでに恋も 止められな~い♪』と、歌っている。と同時に運転中のダンナは、『雪のォ~ 谷間にィ~ ワカメ酒ぇ~♪』と、まったくちがう唄を歌っている。
と、書きながら自分が爆笑したのだが、字で読むといまいちウケないかな? にしてもコレは今作の、えせメルヘンでありつつブルジョワ臭をキツぅく発し、さらには『そうとしても奇妙』であるふんいきを、一瞬で伝えている1コマではないかと。かつまたこのハト夫婦の関係の、すれちがっているのかみごとにシンクロしているのか、よく分からないところが出ている部位でもありつつ。
あと1つ、異なるところを見ておくと。ハトよめがムスコの≪ブッコちゃん≫に、おうちでTVゲームばかりしてないで『初めての おつかいに 行ってきなさい』、と言って≪1600円札≫を渡す。追って、いさいは略すがブッコちゃんがそのお札を出してミネラルウォーター『ビビッテル』を買うと、店主がおつりに≪1450円札≫をくれる(第2巻, p.133, 『ハトビームの30』)。
筆者はコレを初めて見たとき、≪1600円札≫や≪1450円札≫などというものの死に物狂いなありえなさに、息が止まるかとばかり爆笑したのだった。たぶんこの≪ギャグ≫は、われわれの貨幣制度のくだらなさを告発し、そしてぞんぶんにそれを蹂躙している快挙だと想うのだが…ッ!?


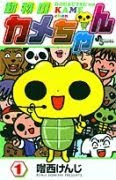
 超ウェルカム! アンド、サンキュー・ベラマッチャ! ここんちは、ギャグマンガ等をレビューしている感じのブログでゲソ! ミーは人呼んでアイスマン、おひとつシクヨロ! ぜひお気軽に皆さまのご意見ご感想を、コメントやメールでアレしてちょ!
超ウェルカム! アンド、サンキュー・ベラマッチャ! ここんちは、ギャグマンガ等をレビューしている感じのブログでゲソ! ミーは人呼んでアイスマン、おひとつシクヨロ! ぜひお気軽に皆さまのご意見ご感想を、コメントやメールでアレしてちょ!

