参考リンク:
Wikipedia「OMEGA TRIBE」
【Ch.1】 俺は、母を犯し、父を殺す(つもり)
≪精神分析≫というものに対しての、こういう見方がある。すなわち、『“すべて”の問題を、“パパ-ママ-ボク”の三者関係トライアングルの問題へと還元しすぎ』、だとか。筆者はあんまり知らないが、世にも名高いドゥルーズ+ガタリ「アンチ・オイディプス」という書物の主張が、ほぼそういう感じらしい。
という話を、ちょっと頭のすみにでも置いた上で、この堕文の主題たる玉井雪雄「OMEGA TRIBE(オメガ・トライブ)」というまんが作品を眺めれば? その訴えるところは「アンチ・オイディプス」とは正反対に、『“すべて”の問題の根源は、親子の問題である』というところかも…という気がしてくるのだった。よってこの作品に対し、「オイディプス・リターンズ」、「バック・トゥ・オイディプス」、といった副題を献上してみるのも、頭の中の自由というものだ。
とまで申してから、今作こと「OMEGA TRIBE」のあらましをざっとご紹介。まず発端、アフリカの奥地で遭難して死にかけた日本の少年が、神とも悪魔ともつかぬ怪しい人物≪Will≫によって、次世代の人類へと≪進化≫させられる。ヒーロー以外には不可視な『怪しい人物』の正体は、異種間の遺伝子の移動を媒介するウイルスだ。
これによってわれらのヒーローたる少年は、単に一種のエスパーとして蘇生したのみか、新人類の仲間を増やしつつ現生人類を滅亡に導く、という義務を負ってしまう。しかもすでに現れている新人類は、彼だけではない。よってわれらのヒーローは、他の系統の新人類たちがひそかに繰り広げている主導権抗争にも、巻き込まれてしまうのだった。
というわけで本編は、『超能力バトル』と『ポリティカルアクション』とをまたにかけたような描写を中心に展開する。…のだが筆者には、今作の決定的な『主題』は≪親-と-子≫、その葛藤、というところかと読める。
何しろまず、ヒーローたる≪吾妻晴(あずま・はる)クン≫が冒頭で瀕死の大ピンチに陥った理由が、『実の父によって殺されかけて』、というものだ(!)。それも、創世記にある『アブラハム×イサク』のような崇高味あるお話ではない。こともあろうに晴クンの父は、『金に困ったので』という理由にて、いらない子であるひきこもりの晴クンを使った保険金サギをもくろみ、わざわざアフリカ奥地まで連れ出して彼を殺そうとしたのだった。
これを筆頭に「OMEGA TRIBE」の主要な登場人物らはいちように、『親への恨み』というものをかかえている。追って晴クンの最大のパートナーとなる暴走族のリーダー≪秋一≫は、母に愛されない子として育ち、彼の想念の中では『自分は母を殺した人間だ』と思い込んでいる。アメリカ新人類のリーダー≪イブ≫は孤児で、幼いころに養父から性的虐待を受けていた。中国新人類から寝返って晴クンらにくみする≪水華≫は、中国の闇のボスである実父のあんまりな冷酷非道さを耐ええない。そして中東新人類の≪ハキム王子≫は、愛なくして彼を産んだ母親への両面感情に苦しんでおり…等々々々。
この作中で≪Will≫を名のる怪しい人物(=ウイルス)は、『おまえの絶望の深さを見せてみろ』、的なことをしばしば言う。現にあるこの世界をどれだけ強く激しく憎んでいるか、それが十分でなければ、新人類として生まれ変わることができないという。
そうして作中人物らが自分の≪絶望≫を掘り下げていくと、その核にあるのが、さきから述べている親への恨みなのだ。それぞれの人物らを『そのようなもの』にあらしめている決定的な≪外傷≫は、それなのだ。そうでない例として目立つのは1件だけ、イタリア新人類の≪ルチアーニ≫、彼の絶望の核は第二次大戦中の収容所体験だ。
で、見ておれば、作中でその『親への恨み』という≪絶望≫をさらけ出した人物らは、いずれは晴クンにくみするようになる(ラスト近くに重大な例外もありつつ)。またサイドストーリーにて描かれた自衛隊員父子の葛藤については、父親が晴クンにくみし息子が敵に廻るのだが、父は親としての自分を深く≪絶望≫してるに対し、息子の方は父への甘えを棄て切れていない…という違いがそれらをさせているのかと。
ただしこの甘ちゃんな息子隊員にしても、彼にその≪行為≫をさせている要因は『十分に愛してくれなかった』という『親への恨み』だ…という形式で、晴クンと一致している。異なるのは、その『十分には得られなかった』と彼が感じている父からの愛を、いまからでも取り戻せるはず…と信じていることだ。ゆえにこの人物には、≪絶望≫が乏しい。それこれにより彼は、晴クンへの対立軸の1つとしてどうにか機能しつつも、小物に終わる。
そして。そうして晴クン(ら)が自分らを組織化しつつ、当面の目標として実行しようとするプロジェクトは、クーデターによる日本の権力掌握だ。
この『クーデター』という語が登場するのは今作の第4巻めだが、全25巻と数えられる今作の以後ほとんどは、その目標の追求を描くことにあてられている。一見して異なることが描かれていても、それらはクーデター実行にいたるための迂回かのように読める。逆に申せば晴クン(ら)は物語の中で、クーデターを成功させたら次にどうするか…までは、あまり考えていないようす。
今作中でさいしょに『クーデター』という語を発したイブは、彼女のアジトへと強制的にご招待された晴クンに向かい、『新人類たちの権力ゲームに参加する気なら、最小限そのくらいは自力で達成してからネ』と宣告する。しかし晴クンの反応がパッとしないので、『さもなくばアメリカがしかけてアメリカの都合いいように、日本の政権を転覆する』のように言って、彼への挑撥を重ねる。この時点でのイブの肩書きは、何とファーストレディ=アメリカ大統領夫人だ(!)。よって、『力こそ正義なり』的な論法と恫喝外交はお手のもの(!?)。
その他もろもろ、その場にてさんざんなる屈辱をこうむった末に、晴クンはイブの挑撥を受けて立つ。ただし、向こうの思惑に乗ったのではないというつもりだ。言わば『ひきこもりの代表』として彼は、アメリカが代表している『強者の論理』の下で苦しんでいる人々を解放するために、クーデターを実行してやると、宣言したのだった。
…という、晴クンの『回心』にもとづくおしゃべりはひじょうに心にふれるものだが、しかしその場でイブが『面白いけど意味不明』と評したように支離滅裂ぎみ。その中に論理の飛躍がない、とはとても思えない。よって、うまくは要約しきれないことを申し開きしつつ。
そうしてイブのもとからの帰り際、人知れず彼にくっついているWillに向かって晴クンは、ひそやかに強力にいわく…。
『俺は、
俺を産み捨てた
母{日本}を犯し、
父{アメリカ}を殺す。』(第4巻, p.87。{}内はルビ)
このフレーズはもちろん、クーデターの実行によってそれを達成にかかる…という意味かと読んでおくが。しかし何をさしてのことであれ、これぞ断固たる≪オイディプス宣言≫としか受けとりようがない。
そしてこの場面は、古い洋楽ロックについて多少とも明るい人々の脳裡に『ああ、ドアーズのジ・エンドか』…という感想を一律に呼び起こしつつ、今作の終盤、その楽曲の訳詞が延々と引用される大山場へ向けての予告、言わば予定調和へのレールの敷設、かとも受けとめられる。
かくて≪覚悟完了≫をキメたところから、晴クンには気弱なお坊ちゃんという性格が失くなり、そしてストーリーの『本編』的な部分が、やっとここから始まるのだった。
ところで≪エディプス・コンプレックス≫という概念についてだが、『正常な人間、誰しもそれはある(必ずそこを経過する)』…と、精神分析は主張する。それがひじょうにないような主体の方が、よっぽどひどく病理的かと考えられる。
しかし常人らにおいて、じっさいに父を殺す、母を犯すということは『ない』。そうしたいけどそうしない、何かその代わりになるようなことらをする、と経過するのが常人の道すじだ。
すると、『本当にやりたいことをやらない』という選択がなされてこそ、ヒトの生きる道はやっと開かれる(!)。このことを精神分析の用語で、≪象徴的去勢≫と呼ぶ。“それそのもの”を実行しちゃったら、まさしく『ジ・エンド』…というところで、ドアーズの唄はまったくもって正しい。
またその一方、ソポクレスの描いた≪オイディプス王≫は、父とは知らずに殺し、母とは知らずに交わってしまったものを、『それをやりたい!』的な概念の代名詞にされては、少々とばっちり気味のようだが。けれども精神分析チックな理屈のいやなところで、『じっさいのところ、それをやってしまった理由は“やりたかったから”に相違ない』と解釈されうる。
【Ch.2】 エディプス期の遅れすぎな到来
とまでを見てから「OMEGA TRIBE」の話に戻ると、晴クンらがやろうとしているクーデターは、『ジ・エンド』を期してのものなのか、そうでなくもっと前向きなものなのか…ということが問題になってくる気がする。けれどもそこは、けっきょく大してハッキリはしていないこと、かと読めた。
彼たちは『クーデターの達成』、せめてその実行、ということに向かってまっしぐらに動いており、その後はどうするということを、深く考えているようすがない。そのようなプランのなさは社会的には大迷惑な感じだが、けれどお話の流れの中では、一種の心理的な自然さを有する。
なぜならば晴クンらの実行しようとしているクーデターは、発達上のプロセスで幼児が初めて親に反抗すること、それと心理的に等価なイベントだからだ。『反抗してどうなる?』ということをチャンと考えている幼児などいないように、晴クンたちもそれを考えていないのだ。逆に申せば晴クンとその軍団の中核は、幼児の時代にふつうの反抗をしなかった、できなかった…という連中なのだ。
かって精神分析の描いた『ノーマルな発達プロセス』という絵図があり、すなわち幼児らはいっときを変態性欲のあくなき追求に捧げ(=多形倒錯)、けれどもやがて、その性欲の発露は≪父≫的な存在からの制止に遭う。ここに≪エディプス期≫というものが始まるが(めやす的には3~5歳ごろ)、やがて幼児らは『父を殺し母を犯す』ということを断念して、性欲の追求自体が≪抑圧≫される。ここに≪潜在期≫が始まり、性欲自体がないかのようにも見える少年少女、というその状態が、思春期の到来まで続く…という予定。
けれどいまどきの『この社会』に、このような規範的な発達プロセスというものが『ない』。…とまで断言するのを控えれば、それがめっきり乏しい。
まずは、≪潜在期≫における『性欲の抑圧』ということだが。フロイトはそれを健全な発達には必須な過程と言い、そしてよからぬ大人等の悪影響で、思春期前の早すぎる『春のめざめ』が生じることを懸念していた。しかしその懸念を、メディア等による性的情報のはんらんがあっさりと実現してくれた。
そういえば筆者にしても、「ハレンチ学園」や「がきデカ」を超・熱読しながら育ってしまった人間なので…。つまり思春期前から過剰にエッチな子どもだったので、『現代社会のひずみの犠牲者』を自認するにやぶさかでない(!?)。…ただし別のところにてフロイトは、『この現代の“性教育”とやらは偽善的すぎる!』のようにも述べておられつつ。
という≪潜在期≫の消失を追って、さらに、≪エディプス期≫の消失ということが起こっていると考えられる。3~5歳といった時期の幼児において、いまや『適切な反抗』がなされにくいのはなぜなのか、少子化の影響などありそうな気もするが、詳しいところは育児や教育の専門家らにたずねていただきたい。ともあれ、現にわれわれの目の前に、多数の≪晴クン≫たちがいるのだ。すなわち、
『俺は、俺を産み捨てた母を犯し、父を殺す。』
この発言が出たところで初めて彼の、いびつなるエディプス期が始まっているのだ(…そこでの年齢は、推定17歳くらい?)。かくて潜在期の消失は『萌えオタ』や『変態紳士』たちの登場を呼び、またエディプス期の到来の著しい遅延は、家庭内暴力やひきこもりの発生を促す。つまりこう言うとあんまりなようだが、晴クンらが実行を期しているクーデターは、大がかりすぎる家庭内暴力だと言ってもよさげ。
…なお、付言して。エディプス期や潜在期に関し、その消失や時期の乱れの影響は、女子らには相対的に小さく、男子らには大だ、と見ておく。
なぜ女子らへの影響が小かと申すと、さいしょから女子らにおいては男子らに比し、それらの発現や効果が劇的でも局時的でもないからだ。それはまたなぜか…というとこの場では語りきれないが、にしても示した見方は、われわれの見ている『この社会』の現況に、そこそこマッチしているのでは?
そして、『家庭内暴力』…この場合だと子から親への暴力は、けっしてよくはないことではあろうけど。だがしかし、『何の意味もない蛮行』でも、けっしてない。ともかくもそれはその家庭の中に、何らかの小さからぬ問題があることを示す指標たりうる。
「OMEGA TRIBE」という作品にて晴クンが言う、『矛盾』。『この世界』、『この社会』、およびその社会の末端の単位たる『家庭』らの中に、無数に存在している矛盾。それらのあつれきを一身に受けとめるようなはめに陥って、そして黙って自殺していく子どもたちがいる。それに対する一方の、無意味げな暴力をふるうことやひきこもる≪行為≫らは、『しかし死にたくはない!』という子どもたちの意思表示に他ならない。
そしてその『しかし死にたくはない!』という無言の叫びこそが晴クンを、アフリカ奥地での絶望もきわまった大ピンチから、この世での活動に呼び戻したのだ。
かつ、一見まともそうな親たちでさえも、その子らに『死の寸前』的な矛盾と苦痛を背負わせている場合があることを考えると、まったくまともでない父によって殺されかけた晴クンの受難は、それらの苦痛を最大限に先鋭化させたものかと受けとれる。ゆえにきわまったる≪絶望≫によって、われらのヒーローには新人類たる資格がある…というわけだ。
と、ここまでに『ひきこもり』という例が出ているけれど、作中ではそれを筆頭に、のけもの・はぐれ・不適応者らにこそ、次なる進化へのチャンスがある…と言われる。これは今日の進化論の、ノーマルで一般的な主張でもある。
ところで晴クンらの期するクーデターの意味あいを、『いま、親子関係を見直せ!』というメッセージのプロモーション、と言うこともできそうだ(“家庭内暴力”の意味するところも、同じでありつつ)。そうして言われた『親子関係』が通常の親子だけでなく、『パパ(米)-ママ(日)-ボク』の象徴的な三者関係でもあるとは、すでに晴クンが明言している通り(…適切かどうかはさておいて、彼によるこの見方は、社会・政治・国際関係の問題らを、例のトライアングルへと還元している。つまり、『バック・トゥ・オイディプス』的な言説)。
ただし、『それらを、“こういうふうに”見直せ』という具体性が、晴クンの側にはとりあえずない。見た目的にはキッチリと計画的だが、実質的には破れかぶれの反抗である彼たちの≪行為≫の見通しのなさを、筆者は『そんなには』、責められないわけだが…。せいぜい言えることは、『愛されなくて苦しんだ者が救われようとするならば、まずはどうにか他者(ら)を愛してみては?』…くらいだが…。
しかしその一方で、他の新人類らの側には、『“すべて”の問題の根源たる親子の問題を、生殖のスタイルの改変でスッキリ解消してしまおう』、というプランらが存在する。ここはひじょうに興味深いので見ておくと、そのプランらを粗雑にも形容してみれば、『託卵』・『分裂』・『三叉生殖』の3種類。
さいごの1つは、男女いずれかの第3者が生殖に参加する『3P婚』(!?)…というゆかいなしろものだ。これはまた、フロイトが型を作りラカンが黄金のメッキをかけた『パパ-ママ-ボク』の聖三角形のエンブレム、それに茶々をぶち込んでいびつな四角形にしてしまおうという壮挙(, 暴挙, 愚挙)なのかっ?
等々あたりの今作の展開は、SF史上初めて性とジェンダーの問題へとシリアスに取りくんだル・グインの名作「闇の左手」を、ちらりと想起させたりもしつつ。かつまた、かの世に名高き「アンチ・オイディプス」の著者らは『n個の性』という超空想的な珍説を提示したらしいが(これも一種のSF的発想?)、そこらへの皮肉っぽい言及をもおぼろげに感じつつ。
そして、ネタバレになってしまうが常識で判断しうることなので、いっそ明記しておこう。「OMEGA TRIBE」作中に描かれたこれら3つの新規なソリューションらは、1つも成功しない。そりゃふつうに常識で考えて、成功するわけがない。
そもそも『新規』とは形容できない後ろ向きな策が前2者、また、単に『新奇』な場当たりのソリューションでしかないのが後1者。つまり、生物としてのレベルで人類の『親子関係を見直す』という問題提起には、適切で有益な解決が存在しそうもない。この見通しは正しい。
またそれらの失敗を見て思い出されるのは、初対面の時点でイブが晴クンに対して、『実は本当に新しい“新人類”は、唯一あなただけ』のように、ハッキリ告げていることだ。つまり、晴クン以外の見かけ上の新人類らは“実は”、現生人類へと進化しそこねた旧人類でしかない。そんな彼らには、単独で将来的な勝利を収める見込みなど、最初から皆無だったのだ。
まったくハッキリとそれは描かれていながら、しかし作品の大部分を占める抗争の描写の長々しさとトリッキーさと激烈さに気を取られ、そんな伏線を筆者はスッキリと忘れていたのだった。これは筆者の頭がとても悪いということなのか、またはそういう風にと仕向けた構成になっているということなのか…?
そういえば『親子関係を見直す』という問題提起に関連してわれわれは、かってカンボジアのポル-ポト派の残虐非道と言うにもあまりな社会実験を見ている。かつそのモデルは、中国の文化大革命の『造反有理』。…ということばの響きはよいが、しかし『党の指導下に』子らが親らを裁くという、これまた残虐にして無謀な実践であり。
またそれらと並行し、今作「OMEGA TRIBE」にはるか先行したSFまんがの手塚治虫「火の鳥 未来編」には、文字通りの『マザー・コンピューター』が生殖と養育を専権的に実行する…などというプランの提示もあった。けれど史実にもフィクションにも、それらの制度的・技術的な『親子関係の見直し』には、ただ1コの成功例もない。唯一、『限定的には成功例なのか?』とも見られうるのは、イスラエルの『キブツ』という制度だけだ(…これについて、もちろん筆者はよく知らない。なぜなのか、現在はすたれ気味らしい)。
もう1つポイントの存在を指摘しておくと、制度的でも技術的でもない『なしくずしの変化』として現在のアメリカでは、シングルマザーの大規模な増加と、結婚・離婚の反復による家庭環境の複雑化が生じているのだとか。後者については、もとの配偶者の連れ子を連れて再婚…ということがまれでない、のような話も聞く。
とすれば。「OMEGA TRIBE」作中で『3P婚』がさいしょに発生し普及するのがアメリカなのだが、じっさい『3P婚』にも近い複雑でおかしな親子関係が、その国では、すでに発生しているではないか…という気もしてくる。そこらを見た上で今作が描かれていたと考えても、特におかしいことはなさげ。
そして、シングルマザーやマルチプル家族のもとで育った子らは、平均的な家庭の子らに比してどうなのか…特に変わりはないのか…という問いはとうぜんあるわけだが、しかしそこらの実態の追求は、他の方々におまかせしつつ。
また。一見まったく関係なさげことも付記しておくと、「OMEGA TRIBE」に現れた『3P婚』ともいうべきアイディアについて、美川べるの「青春ばくはつ劇場」という4コマのギャグ作品が、異なる切り口で描いている。
すなわち、そのシリーズのヒロインで女子高校生の≪麗≫が電器店を訪れ、『親子電話がほしいんですが』と言う。すると店員は、『こちらのは子機が5台もついて便利ですよ』と言う。
『うーん、子機はそんなにいらないです』
『ならば、こちらはいかが! 子機が1台に対して親機が3台、という画期的商品です!』
『…ふつうの親子電話をください』(「青春ばくはつ劇場」第4巻, 2009, p.61より、自由な要約)
こうしたすぐれたギャグ作品を見ていると、同じようなことを描いて≪ギャグまんが≫は4コマ1本であざやかにサッサと済まし、一方のギャグでないまんが作品らは数百数千ページをムダに…あ、いや、過剰にページ数を費やす、という事実は知れる。これすなわちフロイトが、≪機知≫という知性のスタイルを大いに賞揚しているゆえんでありつつ。
【Ch.3】 意味=享楽、その回帰まで
かつ、『親子関係の見直し』について、とくべつによさげなソリューションは存在しない、ということに並行し。もし人類にこの先の進化があるものとしても、その方向性が、今作「OMEGA TRIBE」にも描かれた『超能力バトル』で勝てるような『能力』の獲得…だとしたら、とうぜんひじょうにおかしい。それはありえない。
つまりガチのタイマンだと人間は、ライオンにもクマにも勝てっこない。…かの範馬バキ君や、そのお父さんでない限りは(…と名前の出た「バキ」シリーズもまた、親子の葛藤をテーマに描かれた作品、つまりもう1つの『オイディプス物語』かと見ゆる)。けれどもしかし、そうかと言って、ライオンやクマの方が人間よりも進化した高等な生物だとは、誰も考えていない。
また。SF設定の『超能力』について、原始人やその前の動物らがそなえていた『第6感』の復活(?)、なんて説明も聞かれるが…。
しかし、もしも先行人類や類人猿らが持っていた『第6感』を現生人類が持っていないとすれば、それは必要でもないし特に便利でもなかったからだ。先祖のサル類が持っていて人類が持たざる、小器用な木登りの『能力』…そのあたりと選ぶところはなさげ。で、そんな要らざる特殊な『能力』らを捨て去ることこそが、つまり≪進化≫なのだ、とも言いたいところだ。
われわれこと現生人類は、服を着なければ風邪をひき、靴を履かなければろくに歩けず、武器を持たなければ草食獣とのケンカにも平気で負ける。まったくもってふしぎなほどに、ひよわな生物ではある。ところがそれらは、まさしく≪進化≫の結果としてそうなっている…ということを認める必要はある。
筆者は先日、『ナショナル・ジオグラフィック』のHPで、『人間は4万年前から靴を履いていたことが判明』(
*)との記事を見た(従来の定説より、約1万年も古くから)。かってながら、これには大いにうなづけるものがある。本来は要らないものである靴というアイテムを、ただの気まぐれでわれわれの大多数がそうびしている…ということは『ない』。いやしくもホモ・サピエンスたるものが外を歩くには、基本的に靴は必要、と考えるべきだ。
そういえば今作「OMEGA TRIBE」の開巻そうそう、約3万年前に、それまで並行して存在していた人類たるネアンデルタール人らを、現生人類が『絶滅に追いやった』…という記述があり、そしてそのページの画面には、後者から前者への一方的な殺戮が描かれている。このナレーションと画面とのびみょうな乖離が、ちょっと興味をひかれるところではある。
すなわち、現生人類がネアンデルタール人らを『直接に』滅ぼしたという見方は、現在までの定説ではない。むしろその説は今後にわたり、すたれていく気配だ。
そうでなく、直接の殺し合いなどはなかったとしても、同じニッチ(生態的地位)を争う2つの種は、いずれ劣勢な一方が滅びる(永続的な共存はない)…という原則がまずありつつ。そしてネアンデルタール人が劣勢となった理由として近年言われているのは、繁殖能力の乏しさ、発話機能(=言語能力)の貧しさ、といったところ。
『(ネアンデルタール人の特徴の1つとして、)現生人類と比べ、喉の奥(上気道)が短い。このため、分節言語を発声する能力が低かった可能性が議論されている。』(Wikipedia Japanより)
おサルに言語が操れないのは、単にお脳が弱いからばかりでなく、発声器官が貧弱だから…と言われる。その逆にカラスや九官鳥らは、まったく理解していなくとも人語をマネして発声できる。人間らが≪記号≫として用いたフレーズを、九官鳥らは≪信号≫として人間らに返している、という感じもする。
で、もしも『分節言語』(=われわれの常用するふつうの言語)がなかったとすれば、彼らと現生人類との優劣は決定的で致命的だ。それがないということは、この堕文が、『ウホホッ、ムホホッホ~イッ』といったような文字列だけでビッシリと埋められており、しかもニュアンスで理解してくれ、的なことだ(!)。
もっとかわゆくネコ語で『にゃにゃにゃん、にゃあ~ん!』と書いてもいいが、ともあれ『分節言語』なしの発話では、発話者のきげんがいいとか悪いとか、その程度のことしか伝達できない。つまり、記号ならぬ信号であるしかない。いくらこれが堕文中の堕文でも、それより少しくらいは『読めそう』なものなのではと、自分では大いに自負しつつ!
見かけ上は言語活動の外側に、『指をさす』という伝達の仕方がある。だが、そんなものでも意外に高度なコミュニケーションなようで、乳児や動物(加えて、ひじょうに重い認知症の方)たちは、示された指自体を眺めるばかりだ。しょうがないので自分が顔ごとソッチを向くと、つられて彼らも同じ方を見る、ということはある。『分節言語』のない世界とは、そのような伝達しかない世界にちがいない。
それこれを考えれば、『じゃんけんぽん、アッチむいてホイ!』といった遊びを愉しめる…そんなことがすでに、われら人類の知能のすばらしさをまたく証明している、かとも見れてくる。『指さされた方を向く』という作業自体がすでに高度であるに加え、『指さされた方を、“向かない”』というそこでのルールまでも理解せねばならないのだから! ついでに申してジャンケンの『チョキ』という手つきがもうすでに、人間ならぬ動物らにはできないし…(カニさんは別にして)。
そしてゲームに失敗するものがあれば、ふつうその場の人々が笑い崩れる…それは『所定でありかつ恣意的なルールのある“遊び”』という理解がちゃんと共有されている証拠なわけで、かくて根源的に考えたら人間らの所業らは、ごくごく小さなことまでが宇宙の中に輝く奇跡、としか思えない! 「ジョジョ」シリーズの荒木飛呂彦先生ではないが、その一貫して言われる『人間讃歌』ということばが、ここらで脳裡に浮かばないわけにはいかない。『人間という生き物のすばらしさ』とは、ノーベル賞学者や五輪のメダリストら『だけ』をさして言われるのでは、けっしてない!
かつまた、『人語(=分節言語)』を解する者は、動物であれども喰ってはならない…とは、ご存じC.S.ルイス「ナルニア・サーガ」中の掟だが。逆にここまで考えてきたら、『分節言語』をまったく有しない者は人類にあらずとみて、別にどうしようとも?…という気がしてきてしまった(!)。そんなでは『現生人類によるネアンデルタール人の虐殺』という仮説に心理的な根拠(?)を与えているようだが、しかしその説には、強い根拠はないのだ。
という『根拠の薄さ』を分かった上でも強い『ヒキ』を作ろうとして、今作こと「OMEGA TRIBE」の冒頭シーンでは、ナレーションと画面の描写とのびみょうな乖離が演出されているのかも?…などとは思ったのだが。が、けれども別に、そんなげすっぽいかんぐりに固執はしない。
ところでさいご、今作のほとんどさいご近く、わりと遠めの近未来あたりのところだが…。以下のネタバレはさすがにちょっとよくないかとも思いつつ、しかし書いておけば。
いろいろあったあげく、いちどは『適応者』として地球上に、最大の勢力を誇った『3P婚』の方々。作中の用語では、『三者人(トリプル)』と呼ばれる新人類。しかし彼らは、ただ単にそこでの現況に『適応』してしまったものとしての、自分らの将来的な限界を悟る。
そして『三者人』らの代表らしき人物は、まったく何の取りえもなさそうな…何でもない凡人どころかむしろ、社会からズルズルと落伍しかけの老けぎみな日本の青年をたずね、『キミこそが次世代人類の父祖になるのだ』のように告げて彼を祝福する。
まったく何でもないということが、未来の何かであるための条件なのだ…というテーゼが、ここにて正しく確認されている。そして、ぜんぜん理解できないままにふしぎな祝福を受けてしまった青年は、それをきっかけにそこまでの彼の考えをちょっと変えて、大急ぎで病院へと向かう。
病院で待っていたのは彼の妻と、そして産まれたばかりの彼たちの子どもだ。そうして彼は、彼とその生きる衰退した日本社会が、ままならぬ失意や逆境の中にあることを認めつつも、しかしあらためて、心から、彼らの子どもの誕生を喜ぶのだ。
ここでわれわれの物語は、『いま、親子関係を見直せ!』という、さきに見た晴クンからのメッセージに戻るのだ。その、親子関係を見直す、再び正しいものとする…ということが新たな人類への道だとして、そこにいたるかんたんな近道の、生物的・技術的・制度的な方策などは1コも存在しないと、すでにわれわれには確認できた(…補助的に有効な方策、くらいはあろうけど)。
よって親子関係をどうにかするには、単に人たるものたちのそれぞれが、正しく望ましき親子関係を作るために、心からつとめるしかない。何せ『まず』その努力がなければ、いっさい何もありえないのだ。というところに、必然性あるものとしての≪オイディプス≫が回帰する。正しい親子関係の中には、いつくしみだけでなく、葛藤もまた必然的にあろう。
などと申し上げている筆者は今作こと「OMEGA TRIBE」の、テーマ性のような部分…そこらへと大いに共感している感じだが。いやじっさい、そうなのだが…。
けれどもしかし、今作の大部分の中身と言える『超能力バトル』と『ポリティカル・アクション』の要素…そこらに対してはそんなにひかれるところがなかったとも、正直に白状いたす。それらは一流のプロのペンによって、十分に面白そうに描かれたページらではありながら。
とは申しても、そこらを単に切って捨てては『物語』がなくなってしまうので、それではまったく何も成り立たないが…。にしても結びふきんのあまりな正しさを見た上では、そこまでさんざんに描写された『超能力』にも『クーデター』にも、それぞれ自体としての大した≪意味≫はなかったではないか、とも感じないわけにはいかない。
と、≪意味≫という語が出たところで1つ申して、この堕文を終わりたい。われわれが今作の決定的な場面と見るところ、『俺は、俺を産み捨てた母を犯し、父を殺す』というあのせりふがポツリと出たシーン。そのすぐ直後に晴クンはキリリと意を決し、渋谷街頭にあふれる群集に向かって、声も限りの大音声で、次のように宣言する。
『俺が、
お前らに、
快楽{意味}を、
与えてやる。』(「OMEGA TRIBE」第4巻, p.92-93, {}内はルビ)
ここに出た、『快楽』と書いて『意味』と読ませる…という晴クンの言語センスは、まったくもっての精神分析に対する挑撥、それ以外の何でもないな…と、ここで筆者はかってきわまる感心をいたしたのだった。ラカン一流の超高等なる理論によれば、フランス語の『ジュイッサンス(享楽)』という語は『ジュ・ウィ・サンス(私は意味を聞く)』、と読み換えられるのだ(…だじゃれ!)。かつラカン用語の≪享楽≫は一般にはない概念だけど、この場面にて晴クンの言った『快楽』は、それへと言い換えられうる。
…けれども。追って晴クンが、たとえば筆者のような凡人らに『享楽=意味』を与えてくれようとして企画したこと…後に晴クンら一味が『祭り』と呼んだもの…つまり、彼らの目論んだクーデター。それが作中の一般人らにとっての『祭り』として機能し彼らにおいての『享楽=意味』が実現されたようすは、ほぼないのだった。これらを見ていた筆者においても、それを受けとった感じがいまいちしない。
【付記】 2010/02/04。文の中盤で、手塚治虫「火の鳥 未来編」についてふれているが、このたびそれを再読してみたら、筆者の記憶とはだいぶ異なるお話だった…ぎゃふん! ではあるけれど、『コンピューター制御の育児』への懐疑を手塚がしつように繰り返し描いている、という事実はある。
また文中、≪オイディプス≫と書いている一方で『“エディプス”・コンプレックス』とも書いている。これは意図的に、一般語と分析用語とで書き分けている。後者の表記は方針として、シェママ他編「新版 精神分析事典」(訳・小出他, 2002, 弘文堂)に従う。
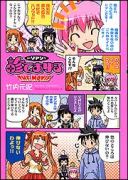












 超ウェルカム! アンド、サンキュー・ベラマッチャ! ここんちは、ギャグマンガ等をレビューしている感じのブログでゲソ! ミーは人呼んでアイスマン、おひとつシクヨロ! ぜひお気軽に皆さまのご意見ご感想を、コメントやメールでアレしてちょ!
超ウェルカム! アンド、サンキュー・ベラマッチャ! ここんちは、ギャグマンガ等をレビューしている感じのブログでゲソ! ミーは人呼んでアイスマン、おひとつシクヨロ! ぜひお気軽に皆さまのご意見ご感想を、コメントやメールでアレしてちょ!

