参考リンク:
Wikipedia「かってに改蔵」
【Ch.1】 伝説の俗物たちをたずねて
『きわめて思い込みがはげしい』とされるヒーローが改造人間になったと思い込んで、学園や地域でへりくつをこねまくる風刺ギャグ。少年サンデーコミックス, 全26巻。
この作品と自分との≪出遭い(そこね)≫についてはよく憶えてて、ソレは1999年の梅雨どき…もう10年以上も前。世田谷に住んでいた当時の自分が、室内に干していても乾かない洗たく物を、近くのコインランドリーの乾燥機で廻していると。そこにその週の少年サンデーが放置されてあり、その掲載誌で読んだのが、今作のわりと初期のエピソード、「こいつは湿気ーだ!!」の巻なのだった(第5巻, p.129)。
読んでおられる方々はご記憶のように、それは作中も梅雨のさなか、『秘密結社 しめしめ団』を名のる奇妙な連中が、主人公らに対して『しめり気礼賛!』というおかしな論陣を張る…というお話であり。
その内容も面白かったがプラスして、そのネタがコインランドリーの待ち時間に、梅雨そぼ降る中で読むにはあまりにもタイムリーで、超ウケちゃッたワケなのだった。【教訓】:やはりギャグまんがッてものも、題材の季節感は大切にせねばならぬ!
という幸福ッぽい≪出遭い(そこね)≫があったわけだが、しかし巻を追うにつれて今作の内容が、みょうに人間のダークサイドをしつように暗く描きがち…となったこともまた、読んでる方々には周知のことかと。具体的に申して筆者は第16巻まで読んで、いったんは今作の読者であることをやめていた。むかしネット上の知人も、『オレもだいたい同じトコでヤメた』と言っていた。
いま見てもごくふつうの感じ方として、この第16巻の後半あたりのエピソードは不快だ。読んでない方のためにいちおう説明しておけば、そこらでヒーローの幼なじみでヒロイン格の≪羽美≫がひじょうにおかしくなり、夜道で改蔵くんを襲撃して瀕死の重傷を負わせる。そしてギャグまんがだからといって、それが次回ではピンピンしている…ということはない。
で、そこにあるようなお話らに対し≪笑い≫を返すのは、常人にはできえざる所業…なんて、自分もたまには常人ぶってみたり。
いっくら今作が、その名も『とらうま町』を舞台とする≪外傷的≫ギャグまんがではあっても、ただ単に≪外傷的≫なことを描けばギャグになる…というわけではない。いやむしろ「改蔵」の行き方として、≪外傷≫のあることは示してもそこを掘り下げているわけではない。
その『どうしようもなくあるもの』としての個有の≪外傷≫が、世間によくいるダメ人間たちのダメさかのように拡散されることにより、この作品は、『外傷的ギャグまんが』が『風刺ギャグまんが』へとすり換えられている。このすり換えのルーチンが、今作のキモといえばそういうところではある。
話が戻って第16巻の巻末、入院中で面会謝絶の改蔵くんについて、『今夜が峠』と医師が言う。ところがそう言われた改蔵くんは、どういうわけだか≪伝説の峠マスター≫たちが集まる山中に出向いている。そこで彼たちは『受験勉強の峠』、『お肌の峠』、『便意の峠』…等々にチャレンジする勇者たちを眺める。
だが、改蔵くん本人が生死の峠をさまよっていることと、それらの勇者たちと、いったい何の関係があるのだろうか? そして、ここでわれわれは、『ギャグまんがだからそれでいい』と言うべきなのか、むしろ生死の境でそんな関係ないことをしているのを≪ギャグ≫と受けとるべきなのか?
そうして失敬だが、作品自体もそこらが≪峠≫という見方が成り立ち、以後は何かひじょうにごまかしてる感じの≪日常≫へと、作品のトーンが復帰している。ただその『ごまかしてる感じの日常』というのがリアルだと言えば、それはそうだ。自慢じゃないけど筆者など、どれだけ多くのことをごまかして生きてきているか…ッ!
【Ch.2】 ≪正気≫に向かって、人を送り出すもの
ところでこんなことを述べてきていたら、2009年の春先にも「かってに改蔵」に、ちょっとかかわるようなことを書いていたのを思い出した。
それがまた異様なしろもので、当時の筆者はご存じの「ひぐらしのなく頃に」のコミック版(原作:竜騎士07, ガンガン・コミックス, 刊行中)について、何かを書こうとしていた。それが『あれもこれも』と関連することを次々に書いていたら1冊の本くらいの分量になってしまい(!)、まったく人前に出せるものでなくなった。
その中で、「かってに改蔵」についてふれているのだが。こう言うとするどい方には『サイコなヒロイン』、とつぜん≪鬼≫と化して兇暴化する少女(ら)をフィーチャーしたお話として、両作のつながりはお見通しかも知れない。そしてその『サイコなヒロイン』(ら)を、筆者は≪インダストリアル・ガール≫と命名してみたのだった。
『インダストリアル』とはもちろん『産業的』という意味だが、しかし音楽ジャンルとしては、≪機械と肉体 - 苦痛と快感 - グロテスクと美 - 憎悪と愛 - そして生と死≫といったものらの極端なコントラストをあおり上げながら描出するポップの呼称であり(同じようなものを『ノイズ系』などとも言う)。で、『“萌え萌え”美少女がいきなり鬼と化す』、というコントラストの超激しさを、筆者は「ひぐらし」シリーズに見て。
その一部をここで再利用しようかとしているのだが、話の前提が多くてなかなかむずかしい…。もうひじょうに割り切って、そこまでの≪論≫の流れを説明してしまえば。
◆「ひぐらしのなく頃に」の描いている狂気は、≪娘が父親を去勢する≫というありえざる行為、というモチーフによって集約される。そこで切除されたものは、“過去の事件の被害者の行方不明の片腕”が、≪シニフィアン≫として象徴している。そして娘がそうびする兇悪なぶきは、“それ”の象徴的等価物である。
◆ほんとうなら権威や秩序や理性らを≪象徴≫として示すべき父、しかしあえなく去勢をこうむる父は、具体的人間像としては≪弱い父≫として登場している。そうして≪弱い父≫という類型は、その子らをヒステリーやスキゾフレニーに導く(C.カリガリス「妄想はなぜ必要か - ラカン派の精神病臨床」より, 原著・1991, 訳・小出+西尾, 2008, 岩波書店)。
◆「ひぐらし」シリーズの舞台の≪雛見沢≫を支配している狂気の根源は、≪父≫という記号の排除である。そこで女性たちは≪父≫なるものの去勢にはげみ、一方の男性たちは≪倒錯者=萌えオタ≫として父の権威をパロディ化して横取りしている。
◆関連して。“萌えキャラ”がいきなり鬼と化す、という「ひぐらし」シリーズの特徴があるが、しかし“萌え”の根底をまさぐれば≪鬼≫が出ることは一種の必然である。なぜならば“萌え”というものが愛をよそおったエゴイズムであり、そして≪象徴的去勢≫の否認をめざす趣向、幼児的自己チューのいびつな発展形だからだ。
◆また、“萌えキャラ→鬼”という移行の可能性は、すでに古くも「うる星やつら」のラムちゃんが予告している通り。ただしもちろん、ラムちゃんは狭義の“萌えキャラ”ではない。むしろあらかじめラムちゃんが“萌え”を撥無しているものを、なぜか後世のやからが“萌えは可能である”とかん違いしている。
…と、『ひじょうに割り切った説明』であるものが、すでにあまりにも長い! しかも、よく見ると重複気味だ。さらに要すれば「ひぐらし」では、象徴的な≪父≫の権威の弱まりが、ドラマの中の父らおよび『父性的なもの』らの弱まり、それへの攻撃や排除、として描かれている。
そしてその結果として、≪雛見沢≫の人々は狂気におちいるのだ。そこを支配するのは『狂った母性』であり(作中で具体的には、“オヤシロさま”や土地のボス一家の頭領の老婆として描かれる)、そしてその狂った母性は、兇悪なぶきを手にした≪インダストリアル・ガール≫らを育てるのだ。
とまでを見てから「かってに改蔵」の話に戻り、筆者が『「ひぐらし」論』の中に書き込んだそれの話を再利用しておけば…(次のパラグラフから)。
ここであらためて見てみれば、その『鬼と化す』、「かってに改蔵」のヒロイン≪名取羽美≫にもまた途中から、その父親がいまいち≪父≫っぽくない、かいしょうがひじょうにない、という設定がついているのだった。まず父親が社会に適応できていないのだから、その娘がとんだ電波少女(インダストリアル・ガール)に育ってしまっても、そんなにふしぎはない。それは「ひぐらし」のレナたんにも、同じく言えることとして。
(補足。「ひぐらし」シリーズのヒロインの1人≪レナ≫の父親は、自分らを棄てた前妻からの慰謝料で生活している、気がやさしいだけの小人物)
「改蔵」の1つのストーリーで羽美は、『私 最近 不安定なの!!』と言いながら、『やってはいけないコト』らへの衝動を抑えきれず…。まずは火災報知機のボタンを押してみたり、そして知らないオッサンのハゲ頭をピシャリと叩いてみたり、しまいには踏切の非常停止用スイッチを押しそうになっているところを、同級生の鉄道マニアに見つかってキッツく叱られたり。
という『しては いけない事を してみたい』との≪欲望≫に、そこでは“プチ破壊願望”との呼称がついている(「かってに改蔵」第14巻, 2002, 少年サンデーコミックス, p.77)。申すもよけいなことだけど、久米田センセのお作らには、よくそのような三流心理学チックな用語らが出てくる。言うまでもなくそれらは、特に何も説明せず解決への見通しに役立つでもない(いやまぁ、『名づけるだけでも、大いに意味がある』…とゆう師父らのみ教えも、ありはしつつ)。
しかし正しい理論を学びつつあるわれわれにはそのそれを、暴走している≪超自我≫の命ずるところなのだ…という見方が可能だ。
(補足。≪超自我≫について、J-D.ナシオ「精神分析 7つのキーワード」より。『なによりも超自我は、見せかけ(semblant)の掟であって、無意識的で無分別な掟なのである。この掟の指令があらゆる良心=意識の命令より強まって切迫したものになり、欲望を極限まで推し進めるよう命令するのである』。『犯罪者の超自我が弱いと考えるのは誤りである。逆にもっともおぞましい殺人者の場合、自分の欲望を極限まで実現すべきだと命令してくる超自我の唸り声を抑えきれずにこれに応えたのである』。訳・榎本譲, 1990, 新曜社, p.208)
そしてその≪超自我≫の暴走を抑えきれない羽美においては、人の世の“オキテ”というものがあまり身についていないのでは、という気がするわけだが。…いや、そんなことを申している自分も別に同じなんだけど、それはさておき。
そんなようなドタバタがいちおう展開し終わったところで羽美は、土手っぷちに腰かけて川の流れを見ている父親を発見。どうしたのか聞いてみたら、このおとーさんもまた『やっては いけない事を やってみたくて』、会社を無断欠勤して海に行ったら、そのままクビになっちまッたとぬかすのだった。…へんなうす笑いを、その中年づらに浮かべつつ(同書, p.84)。つまりこの困ッた事態が『実は』、本人にとっては思うツボなのだ。
別に精神分析の文脈じゃなくても言われそうなこととして、≪父≫たるものは家庭において…子どもに対して、≪社会≫の代表、的なところを見せねばならんのでは? その父たるものがこのていたらくでは、羽美がとほうもない≪社会オンチ≫であることを、本人だけの責めに帰すことはできそうにない。
で、さらに見てみると、そのちょっと前のお話にて羽美は、交番をたずねて『人の道を教えて ほしいのですが』などと言っているのだった(同書, p.8)。いたってまじめな表情で、
『どうやら私、少々 人の道をはずれて しまってる感が あるのです』
…と訴えたのだが、しかし巡査はまずビックリし、そして次には気分を害するばかりだ。
『国民年金を 払ってみたり… 他人の赤子に 愛想笑い したり…
そんな当たり前の 人の道は―― どう行けばいい のでしょう?』
ここにて羽美が、言っているようなこと。『当たり前のことらを当たり前にやるためには、どうすればいいのですか?』…のようなやっかいな質問を、平気で人に投げかける方々がいることは、すでにわりと広く知られている。その方々とは、≪スキゾフレニー≫(統合失調症, 分裂病)の患者さんらだ。
このヒロインにはかわいそうだがはっきり言って、そんな質問が出てくること自体が1つのりっぱな≪症候≫に他ならない。別に彼女を≪スキゾフレニー≫なのだ…と断定もしないけれど(オレはお医者サマじゃないので)、しかしここにある眺めをカリガリスによる図式(前掲書, p.85)と照らし合わせたら、ずいぶんに符節が合っている…と、“誰も”が感じるのではなかろうか?
だが念のために付言すれば、実在する父がかいしょうなしだったからといって、その子らが必ず≪精神病≫や≪神経症≫になる…という事実はない。裏返して、真人間っぽい父の子らが必ず正気に育つ…という事実もない。われわれがかんじんだと見ているのは、主体において≪父の隠喩≫が機能しているや否や、とゆうことだ。
そして要請される≪父≫のイメージは、いかなる実在の父をもはるかに超えるほど、りっぱで大きなものなのだ。ゆえに問題は、実在する父の姿がどうか…ということにプラス、主体を囲んでいる家庭や社会が、≪父≫のイメージをどのように描いているか…ということもだ。
ただし時たま気分が変わると(?)羽美は、とうとうと彼女の≪妄想≫を語り、また地球上にはない言語を操り、そして超攻撃的な態度に出る。…と、その病態が≪パラノイア≫チックに遷移したりするのが、チョッとしたごあいきょう。
こういうのが現代のドクター様らを悩ませる、≪境界≫的な症例ってもの? と言ってから「新版 精神分析事典」の≪境界例≫の項目をチェキれば、なるほど羽美タンはこれだなァ…と思わせてくれるものがある。
そうなので扱いにくいだろーが、しかし。レナたんと比べたら羽美という≪症例≫は、こっちの社会の中でもありうるケース、かと思われる。強力にデフォルメされてはありつつも、しかし久米田康治「かってに改蔵」なる創作が描き出しているのは、われわれの住む≪この社会≫と同質の世界だ。
(かつまた改蔵くんが明らかにおたくっぽいこともまた、雛見沢の男子たちがいちように萌えオタであることと対応した、『変質化による父の権威の簒奪』という症候ではある)
…過去の堕文の再利用、ここまで。これを『読めるように』と書き直して筆者がずいぶん疲れたわりに、見た人にはあまり面白くなさそう…。
ところでさいごに、今作の『衝撃的』とされる最終回について、ばくぜんと書いて終わろうとすれば。あらためて社会に向かっていくヒーローとヒロインを、病院の屋上から院長が見送っている。この、ぶしょうひげの中年男である≪院長≫が何ものなのかが、筆者にはよく分からない(第26巻, p.185)。
ただはっきりしているのは彼が、≪正気≫の根拠としてなければならない≪父性≫を象徴するものなのだろう、ということだ。そしてその姿がやはり、細っこくも弱々しくて頼りなさそうなのだった。


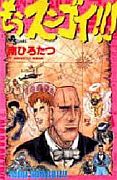
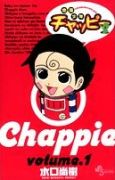
 そういえば先日、自分は伊藤潤二先生の「うずまき」(1998)というお作を読んだ。これがご存じのように、すさまじく『悪夢』的な衝撃ホラー作品だが。
そういえば先日、自分は伊藤潤二先生の「うずまき」(1998)というお作を読んだ。これがご存じのように、すさまじく『悪夢』的な衝撃ホラー作品だが。


 と、それきり疎遠になってしまってから、数週間後。何かのはずみでフェチ君は、次のように自分の考えを改めるのだった(「屈折リーベ」ジェッツ・コミックス版, p.168)。
と、それきり疎遠になってしまってから、数週間後。何かのはずみでフェチ君は、次のように自分の考えを改めるのだった(「屈折リーベ」ジェッツ・コミックス版, p.168)。










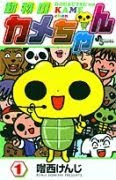



 超ウェルカム! アンド、サンキュー・ベラマッチャ! ここんちは、ギャグマンガ等をレビューしている感じのブログでゲソ! ミーは人呼んでアイスマン、おひとつシクヨロ! ぜひお気軽に皆さまのご意見ご感想を、コメントやメールでアレしてちょ!
超ウェルカム! アンド、サンキュー・ベラマッチャ! ここんちは、ギャグマンガ等をレビューしている感じのブログでゲソ! ミーは人呼んでアイスマン、おひとつシクヨロ! ぜひお気軽に皆さまのご意見ご感想を、コメントやメールでアレしてちょ!

